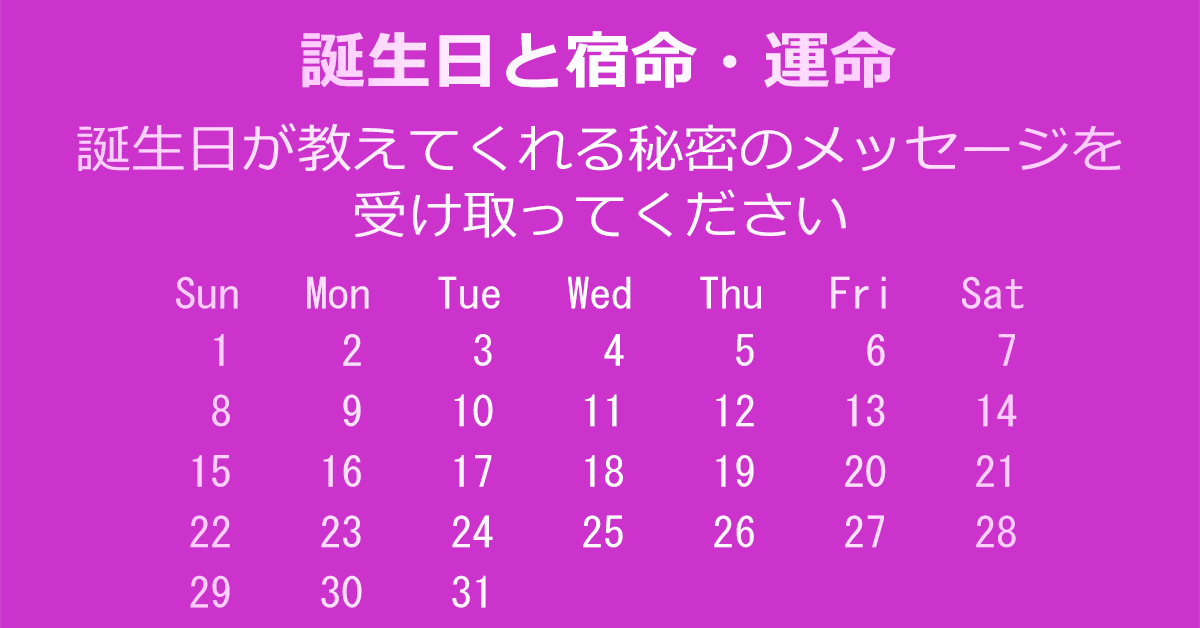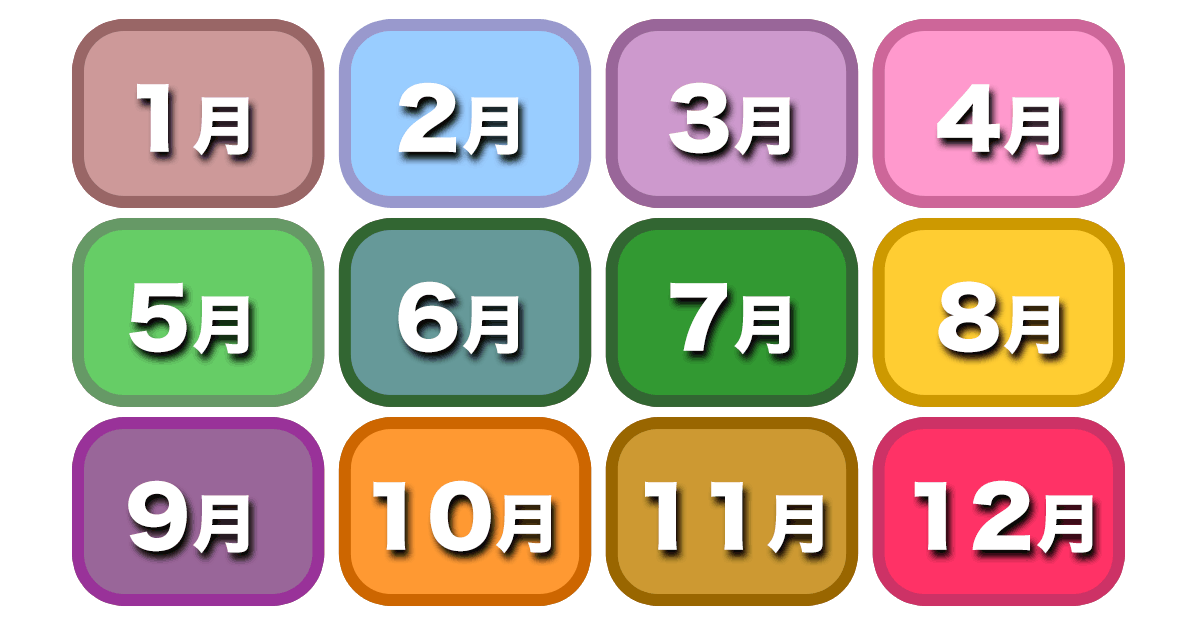1年間に10万円を超える医療費を支払った時は、確定申告にて医療費控除を受けられる可能性があります。
マイナンバー制度が施行されてからは、マイナポータル経由で取得したデータによる確定申告書への自動入力も可能になりました。
今回は、医療費控除の条件とマイナンバーカードを使った申告方法について解説しましょう。
医療費控除の条件は?確定申告で治療費の一部が戻ってくる
1年間に使った医療費が10万円以上になる時、医療費控除を利用すると確定申告で医療費が還付される場合があります。
所得が200万円未満であれば所得金額の5%以上が医療費控除の対象となるので、給与明細などで確認してみましょう。
家計をともにする配偶者や子ども、その他の親族がいる場合は、確定申告を行う本人以外が支払った医療費も合算可能です。
共働き世帯での場合も同様で、例えば妻が扶養に入っていなくても夫と妻の医療費を合算できます。
ただし医療費控除は支払った所得税から還付されるもので、年末調整で所得税が発生しなければ対象になりません。
また、還付される医療費は支払った所得税の額が上限となります。

医療費控除でいくら戻ってくる?受け取った保険金を差し引いて計算しよう
医療費控除を利用すると、実際にいくら戻ってくるか計算してみましょう。
計算式
(1年間に支払った医療費総額ー受け取った保険金など)ー10万円(または所得の5%)=医療費控除額(最高200万円)
怪我や病気、入院などで保険金を受け取った場合は、支払った医療費総額から差し引きます。
所得が200万円以上であれば10万円を超えた分、200万円未満であれば所得の5%を超えた分が控除額となります。
マイナ保険証で簡単申告!医療費を自動入力
医療費控除を受けるには、「医療費控除の明細書」を所得税確定申告書に添付する必要があります。
この明細書には医療機関などから発行された領収書をもとに、「医療を受けた者の氏名」や「医療費の支払先(医療機関・薬局などの名称)」、「医療費の区分」、「支払った医療費の額」などを入力します。
領収書の添付は必要ありませんが、税務署から提出を求められることもあるため、確定申告期限から5年間は保管しておきましょう。
マイナンバーカードを保険証として利用する登録を済ませておくと、確定申告書作成コーナーでのオンライン申請にてマイナポータルから医療費の自動転記が可能になります。
ただし自動診療やドラッグストアでの医療費購入、通院費については反映されないため、自分で情報を入力する必要があります。
医療費控除を受けたい場合は、提出義務のない領収書等も念のため5年間は保管しておくようにしましょう。
また、マイナポータルを使用して医療費情報を取得できるのは本人分のみなので、家族分も合算したい場合は代理人設定が必要です。
詳しくは国税庁の公式サイトなどでご確認ください。